純粋持続の形而上学:ベルクソン時間と「生きられた体験」の再発見
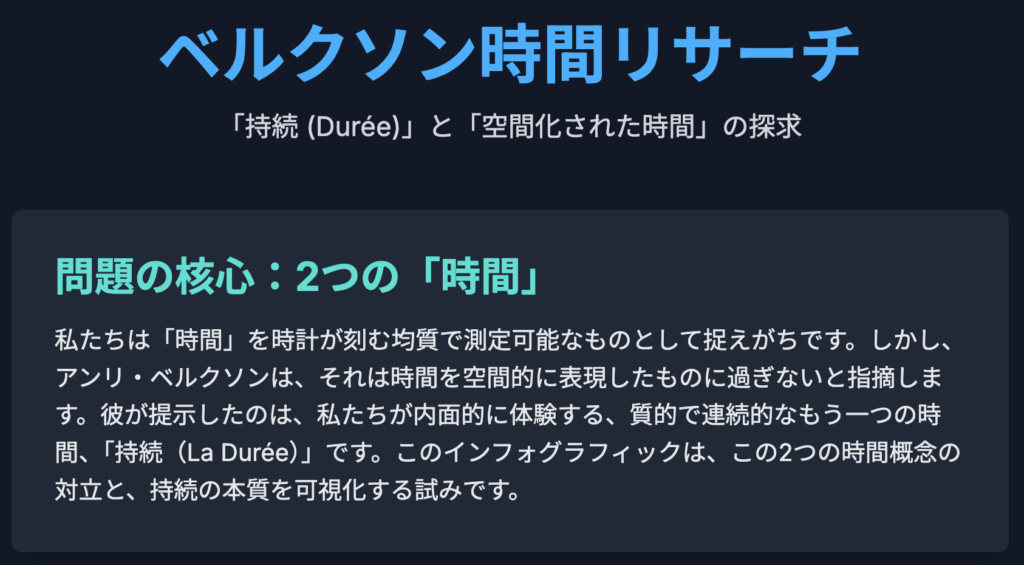
導入:二つの時間と哲学の危機
アンリ・ベルクソンの哲学的企図の全体は、一つの根本的な対立、すなわち「生きられた時間」1と「測定された時間」1との間に横たわる深刻な亀裂をめぐる考察によって推進されている。この対立は、単なる専門的な時間論の区別ではなく、西洋形而上学が直面していた実存的かつ認識論的な危機そのものを表している。
ベルクソンが対峙した19世紀末の知的風景は、主に三つの支配的なパラダイムによって構成されていた。第一に、イマヌエル・カントの枠組みである。カントは、時間と空間を我々の経験を構成する並列的な(a prioriな)直観形式として位置づけた 2。第二に、イギリス経験論に由来する心理的原子論、すなわち連想心理学である 3。これは、意識状態を感覚や観念といった離散的で計数可能な「原子」の集合として扱う。第三に、ニュートン物理学に代表される科学的決定論であり、これは宇宙を支配する均質で普遍的な測定可能な単一の時間を前提としていた。
これら三つのパラダイムは、それぞれ異なる仕方で、ベルクソンが「実在」そのものと見なすものを隠蔽し、歪めている。ベルクソンの「持続」(durée)という概念は、これらの「空間化」された歪曲から「意識の直接与件」3を奪還しようとする、革命的な試みであった。本報告書は、この「ベルクソン時間」が、単なる時間論に留まらず、一つの包括的な哲学的体系、すなわち独自の方法論(直観)、倫理学(自由)、そして宇宙論(エラン・ヴィタール)そのものであることを論証する。
第1部:純粋持続(Durée Réelle)の本性
ベルクソン哲学の基盤は、「純粋持続」(durée réelle)と呼ばれる時間概念の綿密な分析にある。これは、知性によって加工される以前の、意識に直接的に与えられる生の経験そのものである。
1.1. 意識の「第一の実在」
ベルクソンの方法論は、根本において現象学的である。彼は、既存の抽象的な理論や枠組みを一旦括弧に入れ、「意識の直接与件へと還ろうとした」3。この直接与件こそが「純粋持続」である。それは私たちが推論によって「知る」対象ではなく、私たちが「である」流れそのものである。この意味において、持続は私たちにとっての「第一の実在」(la réalité première)である 3。それは、他の全ての実在性を評価するための、そして他の全ての概念(空間、物質、知性)がそこから派生するものとして理解されるべき、原初的な経験である。
1.2. 質的多様性
純粋持続を理解する上で最も重要な概念の一つが、「質的多様性」(multiplicité qualitative)である 3。ベルクソンは、これを「量的多様性」(multiplicité quantitative)と厳格に対比させる。
量的多様性とは、例えば「羊の群れ」や「ビーズのネックレス」のように、空間内に並置され、互いに外在的であり、したがって計数可能な要素の集まりを指す。一方、質的多様性とは、例えば一つのメロディを聞く経験、あるいは徐々に深まる恋愛感情のような、意識状態の流れを特徴づけるものである 3。
メロディの各音符は、それ自体として独立して存在しているのではなく、先行する音符の記憶と、後続する音符への期待の中で、全体の流れの一部としてのみ意味を持つ。同様に、感情の「深まり」も、離散的な「感情の単位」が加算されていくこと(量的増加)ではない。それは、意識の「全体」が、その色合いや緊張において、根本的に「変化」すること(質的変化)である 3。知性が「私はより悲しい」と表現するとき、それはこの質的な変容を、不適切にも「より多い量の悲しみ」として空間的なメタファーで捉え直した結果に過ぎない。
1.3. 相互浸透
質的多様性としての持続の構造は、「相互浸透」(interpénétration)によって特徴づけられる 3。量的多様性の要素が互いに「外」にある(並置)のに対し、持続の諸契機(「過去」と「現在」)は、互いに浸透しあう。
ベルクソンにとって、過去は過ぎ去って消滅したものではない。それは絶えず蓄積され、現在の瞬間に全体として作用し、未来へと自らを押し進める。持続とは、このように過去が現在を内側から膨らませていく、絶えざる「膨張」(gonflement)のプロセスである。
この有機的な連続性を説明するために、ベルクソンは「芸術作品」や「有機的全体」といった比喩を用いる 3。完成した絵画において、個々の筆致は、それ自体としてではなく、作品全体の不可分な表現としてのみ存在する。同様に、純粋持続の中では、「各部分が互いに相互浸透」しており 3、それらを「部分」として切り離すことは、その本性を損なうことである。
1.B1. 表1:時間の二つの概念
このベルクソン哲学の根幹をなす二項対立は、以下の表によって明確化される。この対立は、本報告書の全体を貫く基本的な枠組みである。
| 属性 | 純粋持続 (Durée Réelle) (ベルクソンの実在) | 空間化された時間 (Temps Spatialisé) (知性の歪曲) |
| 本性 | 質的、異種混淆的 (質的多様性) 3 | 量的、均質的 (量的) 3 |
| 構造 | 連続的流れ、「有機的全体」 3 | 離散的、可分的、「数直線」 3 |
| 諸部分の関係 | 相互浸透 (相互浸透する) 3 | 外在的並置 (並立) 2 |
| 経験 | 「生きられた時間」 1 | 「測定の時間」 1 |
| 把握方法 | 直観 (直観) 3 | 分析、知性、言語 2 |
| 比喩 | メロディ、成長する有機体、意識 | 時計、定規、ビーズのネックレス |
第2部:「空間化」(空間化)の病理
ベルクソンによれば、私たちが日常的に「時間」と呼んでいるもののほとんどは、真の持続ではなく、知性によって「空間化」された代用に過ぎない。この「空間化」こそが、哲学が解決すべき根本的な問題である。
2.1. 知性の「原罪」
ベルクソンは、人間の知性、言語、そして社会生活が、本質的に持続を把握「できない」構造になっていると論じる。「私たちは自分たちのことを表現するのに必然的に言葉をもってし、しばしば空間において思考する」2。
知性の基本的な働きは「分析」(analyse)である 2。分析とは、複雑な対象を「既知かつ共通の要素に分解する」2ことで理解しようとする作用である。この作用は、連続的な流れ(持続)を、離散的で静的な「点」や「状態」に分割することを要求する。
言語はこの空間化の主要な媒体である 2。例えば「悲しみ」という言葉は、本来は質的で流動的な経験であるはずのものを、あたかも一個の独立した「対象」であるかのように固定化し、他の「喜び」や「怒り」といった「対象」と並べてしまう。
運動の把握も同様である 3。私たちは、飛んでいく矢の「運動」そのもの(持続)を捉える代わりに、矢が「かつていた位置」と「いまいる位置」という一連の静止した「点」を空間上にプロットし、その軌跡(空間)をもって運動(時間)と取り違える。これが、持続が「空間化・量化されてしまう」3メカニズムである。
2.2. カント批判
この空間化の批判は、カント哲学の核心に向けられる。ベルクソンは、カントが空間を純粋直観(a prioriな形式)としたことには「概して肯定的」である 2。彼にとっての真の問題は、カントが「時間と空間が互いに並立する概念としてあること」を前提とした点にある 2。
ベルクソンの分析によれば、カントが「時間」と呼んだものは、純粋持続では全くない。カントの時間(内的直観の形式)は、空間(外的直観の形式)と「並立」させられた結果、空間の特性、すなわち「均質性」を帯びてしまっている。カントの時間とは、諸現象を収めるための、均質で、空虚な「容器」であり、それは空間の四次元目の軸に他ならない。
ベルクソンはこの序列を逆転させる。彼にとって、実在するのは純粋持続(時間)のみである。私たちが「空間」と呼ぶもの、そしてカントが「時間」(均質な形式)と呼んだもの(空間化された時間)は、その純粋持続の流動を、私たちが「行動」するために固定化し、図式化した派生物(一種の心的ダイアグラム)に過ぎない。
2.3. 空間化の機能:対象の構成
空間化は、単なる哲学的「誤り」ではなく、生物学的な「機能」である。それは、「空間化によって本性を損なって認識されてしまうものがある」2という代償を払ってでも、私たちが獲得しなければならなかった生存戦略である。
『創造的進化』において展開されるように、人間の知性(およびそれが用いる空間化の作用)は、真理を「認識」するためではなく、物質に「作用」するために進化してきた 4。流動的で相互浸透する持続のままでは、私たちは行動を起こすことができない。狩りをするにも、道具を作るにも、私たちはまず、連続的な実在の流れを、安定した、操作可能な「対象」へと「切り分け」なければならない。
この「切り分け」の作用、すなわち「対象を構成する作用」2こそが、空間化の主要な機能である。したがって、空間化(およびその知的側面である「分析」)は、私たちが物質的世界で生き延びるための実用的な能力であり、そのために実在の本性(持続)を歪曲する(本性を損なう)2ことは、避けられない運命であった。この歪曲された像を、実在そのものと取り違えること、それが形而上学の根本的な誤謬である。
第3部:持続と自由(『時間と自由』の論証)
ベルクソンが純粋持続と空間化された時間を区別する最大の目的は、西洋哲学の難問である「自由意志」の問題を、全く新しい仕方で解決(あるいは解消)することにあった。
3.1. 偽のジレンマの解体
ベルクソンは、主著『時間と自由』(原題『意識に直接与えられたものについての試論』)において、決定論(Determinism)と非決定論(Indeterminism)の間の論争全体が、「偽の問題」(faux problème)であると断じる 3。
なぜなら、決定論者も非決定論者も、その前提において「同じ誤り」を犯しているからである。その誤りこそ、時間を「空間化」して捉えることである 3。
- 決定論者は、時間を一本の数直線として表象し、過去の「原因A」が現在の「結果B」を必然的に決定するという「因果の鎖」を想定する。
- 非決定論者もまた、時間を一本の数直線として表象するが、ある「地点A」において、「進路B」と「進路C」への「分岐」が可能であったと主張する。
ベルクソンの批判はこうである。両者ともに、時間は離散的で静的な「点」の連なりであると暗黙裏に仮定している 3。そして、その時間(空間化された図式)の「外」に、選択を行う「主体的自我」なるものが存在すると想定している。しかし、ベルクソンによれば、このような「主体的自我」は、持続から切り離された抽象的な「迷妄」に過ぎない 3。
3.2. 「自由な行為」の再定義
もし自由が、空間化された時間軸の上での「選択」でないとすれば、自由とは一体何なのか。ベルクソンによれば、真の自由とは、稀ではあるが確かに存在する、ある種の行為の「質」を指す。それは、「人格全体の自己表現」(l’expression de la personnalité entière)である 3。
自由な行為とは、その人の蓄積された「過去の全体」(相互浸透する純粋持続)から、有機的に「生い出でる」行為である。
ベルクソンは、この自由な行為を「芸術家」の創造活動に喩える 3。偉大な芸術家が傑作を生み出すとき、彼/彼女は既存の「選択肢」から一つを選んでいるのではない。その行為は、彼/彼女の全人格と全生涯が凝縮された、一つの新しい「創造」である。
この創造的行為は、二つの相反するように見える特徴を持つ。
- 予測不可能性:それが「なされる前」には、誰も(本人でさえも)それを予測することはできない。
- 必然性:それが「なされた後」には、それはその芸術家の全存在と完全に調和し、それ以外あり得なかったかのような「必然性」を帯びて感じられる。
これこそが、ベルクソンの定義する「自由」である。それは、空間化された「選択」ではなく、持続的な「創造」である。この観点から、8で提示されている「何故ベルクソン自身は持続なる概念を持ちだして、自由を説明しようとしたのだろうか」という問いは、決定的な答えを得る。8の論者が求めている「理由」(=空間化された原因)を、ベルクソンはまさに退けているのである。ベルクソンにとって、自由な行為の「理由」とは、その人の人格的持続の「全体」以外にない。
3.3. サルトルによる批判:持続 対 実存
ベルクソンのこの自由論は、後の実存主義者、特にジャン=ポール・サルトルによって批判的に検討される。サルトルは、ベルクソンの自由の解釈を「意志的行為のみに存する」5、つまり、上記のような稀な「創造的行為」に限定されすぎていると批判した。
サルトルはこれに対し、「自由は私の実存そのものに等しい」5と主張する。サルトルにとって、自由とは、過去の持続(サルトル用語で言えば「即自」)から生い出でる稀な真正性の行為ではなく、むしろ、あらゆる瞬間にその過去を「無化」し、ゼロから自らを「投企」する、絶え間ない苦痛に満ちた「選択」(「自由の刑」)である。
これは二つの異なる現象学の衝突である。ベルクソンの自由が、自己の蓄積された持続に「忠実であること」(真正性)の自由であるのに対し、サルトルの自由は、その持続から「切断すること」(ラディカルな選択)の自由である。サルトルの批判は、ベルクソンの自由が、実存主義的な「無からの創造」とは異なる射程を持つことを明確にした。
第4部:アインシュタイン=ベルクソン論争(世界観の衝突)
ベルクソンの時間論が直面した最大の試練は、同時代に登場したアルベルト・アインシュタインの相対性理論であった。
4.1. 1922年の対決
1922年、パリの科学アカデミーで、二人の巨人は直接対面した。このやり取りはしばしば「時間論争」と呼ばれるが、実際には論争というよりも「立場の違いの表明」1であった。
- アインシュタインの立場:物理学者として、彼は「哲学的時間は存在しない。物理学における時間のみが現実だ」1と述べた。彼が扱うのは、観測者によって伸縮し、複数存在しうる「測定の時間」(temps mesuré)である 1。
- ベルクソンの立場:哲学の擁護者として、彼はアインシュタインの相対性理論の「物理学としての正確性」を認めつつも、その哲学的含意を厳しく制限した。「それは生きられた時間を説明しない」1と。ベルクソンが擁護したのは、唯一無二の、質的な「意識の連続としての『持続』(durée)」1であった。
4.2. 科学(数量化) 対 哲学(質)
この「論争」は、単なる時間論に留まらず、20世紀の知の「管轄権」をめぐる代理戦争であった。両者の差異は、「自然を数量化する科学」と「体験を質的に捉える哲学」の間に横たわる「構造的な隔たり」1そのものを示している。
- **科学(アインシュタイン)**は、自然を「数量化」(quantification)する 1。そのために、質的な経験(例えば「同時」の感覚)を、操作可能な測定の手続き(例えば光信号の交換)に置き換えなければならない。
- **哲学(ベルクソン)**は、経験を「質的に捉える」(saisie qualitative)1。哲学にとって、測定手続きの「前」に存在する「生きられた体験」こそが、第一の現実である。
この対立は、1が指摘するように、ニュートンとゲーテの色彩論の対立と通底する。ニュートンは光を(数量的な)波長として「分析」した。ゲーテは色を(質的な)人間の感覚現象として「記述」した。両者は異なる問いに答えており、どちらかが他方を無効にするわけではない。アインシュタインとベルクソンは、異なる「時間」について語っていたがゆえに、最後まで噛み合うことがなかった。
4.B1. 表2:「時間論争」の要約 (1922年)
この両者の「立場の違い」1は、実在の異なるレベルに関するものであり、以下の表のようにまとめられる。
| 側面 | アルベルト・アインシュタイン (物理学) | アンリ・ベルクソン (哲学) |
| 研究対象 | 「測定の時間」 1 | 「生きられた時間」 1 |
| 中核的主張 | 「哲学的時間は存在しない。物理学における時間のみが現実だ。」 1 | 「相対性理論は…生きられた時間を説明しない。」 1 |
| 時間の本性 | 多元的、相対的、観測者依存、時空の一次元 1 | 一元的、絶対的、「意識の流れ」 1 |
| 方法論 | 数量化、測定 1 | 直観、質的把握 1 |
| 世界観 | 「永遠主義」 (Eternalism) 6、時間は地図である | 「現在主義」 (Presentism)、時間は創造的流れである |
| 実在の地位 | 物理学こそが存在論である | 経験(持続)こそが存在論である |
4.3. 現代的融和
この論争は、その後数十年にわたり、物理学の圧倒的な成功の前にベルクソンが「敗北」したと広く見なされてきた。しかし、1が示唆するように、「現代科学が再びベルクソン的視点を必要とし始めている」1。
その最大の理由は、「意識の問題」である。相対性理論が宇宙の時間を支配する一方で、神経科学 1 や意識研究は、脳という物質的・物理的なプロセス(シナプスの発火という「測定の時間」)から、どのようにして「私」の主観的で質的な時間の流れ(「生きられた時間」)が生まれるのか、というベルクソン的な問いに直面している。
この文脈において、アインシュタインの時間とベルクソンの時間は、もはや対立するものではなく、「人間と宇宙のあいだを往復する二重のレンズ」1として、異なるレベルの実在を照らし出すために共存しつつある。
第5部:宇宙的持続(エラン・ヴィタールと創造的進化)
ベルクソンの時間論は、『時間と自由』で展開された個人の心理的な「持続」に留まらない。『創造的進化』において、この「持続」は宇宙論的なスケールへと拡張され、生命と宇宙そのもののエンジンとして再定義される。
5.1. 心理学から宇宙論へ
『創造的進化』において、ベルクソンは「持続」(デューラーション)4を、宇宙全体を貫く創造的なインパルス、すなわち「エラン・ヴィタール」(élan vital、生命の躍動)として捉え直す。エラン・ヴィタールとは、物質という「下り坂」を下降しようとする惰性的な力に対抗し、絶えず新しい形態を「創造的飛躍」4によって生み出そうとする、宇宙的な「時間」の力である。生命の進化とは、このエラン・ヴィタール(=宇宙的持続)が、物質(=空間化されたもの)の抵抗の中で自己を切り開いていくプロセスに他ならない。
5.2. 知性 対 本能 (エラン・ヴィタールの分岐)
このエラン・ヴィタールは、進化の過程で「分岐」(divergence)していく。その最も重要な分岐が、意識の二つの形態、すなわち「知性」と「本能」である。
- 知性 (Intellect):これは第2部で見た「空間化」する能力である 4。知性は、物質(静的なもの)を分析し、操作することに特化している。それは生命の流れの「内部生命の人工的模造物」4を作ることはできるが、流れそのもの(持続)を捉えることは原理的にできない。
- 本能 (Instinct) / 直観 (Intuition):本能は、生命の流れ(持続)を、その「内側」から共感的に把握する能力である。「直観」3とは、この本能が自己意識的になり、自らの対象を明確に把握できるようになった、哲学的な方法論である。
5.3. 現代的射程:AGI問題
この知性と生命(持続)の区別は、現代の汎用人工知能(AGI)開発の問題に直結する 4。
ベルクソン的な見地からすれば、「脳神経模倣型」(脳の物質構造をシミュレートする)アプローチによって得られるAIは、どれほど精巧であっても、生命現象の「外形的・静的なコピー」4に過ぎない。それは知性、すなわち「内部生命の人工的模造物」4を極限まで洗練させたものに過ぎず、そこに生命の本質である「創造的飛躍」や真の「持続」が欠如している可能性がある 4。
AGIの議論は、アインシュタイン論争の現代的な変奏である。すなわち、純粋に「量的」かつ「空間化」されたシステム(コンピュータ、あるいは脳の物理マップ)が、真に「質的」な経験(持続)を「創発」させることができるのか。ベルクソンの哲学は、この問いに対して、厳しくも明確な否定的見通しを提供する。
第6部:持続の遺産(ドゥルーズの潜在的なもの)
ベルクソンの「持続」の概念は、サルトルによる実存主義的な「自由」の文脈での批判 5 とは異なる仕方で、20世紀後半のフランス哲学において決定的な影響を与えた。その最も重要な継承者が、ジル・ドゥルーズである。
6.1. サルトル批判を超えて
ドゥルーズは、ベルクソンの「持続」を、単なる心理学や自由論の概念としてではなく、新しい形而上学の核心として再評価した。ドゥルーズの読解 7 は、持続が「どのようにして」新しいものを「創造」するのか、その内的なメカニズムの解明に焦点を当てる。
6.2. 「否定なき差異」
ドゥルーズによれば、持続は「自己に対して差異を生じる」7ことによって創造を行う。このプロセスは「分化」(différenciation)と呼ばれる。重要なのは、この「分化」が、Aが非Aになるというような「否定」(négation)や「矛盾」(contradiction)を介さないことである。
ベルクソンの「分化」は、「1つのものであるままに『不可分でありつつ可分でもある』」7という、一見すると荒業に見えるプロセスである。これを可能にするメカニズムとして、ドゥルーズはベルクソンの「潜在性・バーチャリテ」(virtualité)の概念を析出する 7。
「潜在的なもの」(The Virtual)とは、純粋な持続(あるいはエラン・ヴィタール)の内に秘められた、まだ現実化(réalisation)されていないが、実在する「傾向性の束」である。例えば、エラン・ヴィタール(潜在性)は、「方向を異にする2つの傾向」(例えば、知性と本能)を「その2つともを含んだ」ものとして内包している 7。進化(現実化)とは、この「潜在性」が、物質的制約の中で、これらの「傾向」を現実の「種」へと分岐させていくプロセスである。
6.3. ベルクソン 対 ヘーゲル
この「潜在性」の発見こそが、ベルクソン哲学の真の革新性であるとドゥルーズは論じる 7。
- ヘーゲルの弁証法は、「矛盾」と「否定」をエンジとする。事物は、「それ自身ではない一切に対して差異を持つゆえに自己に対して差異を持つ」7。差異は、ここでは否定性の産物である。
- ベルクソンの「分化」は、「否定なき差異の概念」7を提示する。事物は、まず「潜在性として自己を実現」7し、「自己に対してまず直接的に差異を生じる」7。
ドゥルーズによれば、「差異は否定よりも矛盾よりも深い」7。「人が矛盾を信じ否定を信じるのは潜在的なものについての無知がゆえである」7。
このドゥルーズによる「潜在性」の形而上学は、ベルクソンシステム全体の統一的な説明原理を提供する。それは、『創造的進化』におけるエラン・ヴィタールの「分岐」4を説明し、また『時間と自由』における「自由な行為」3が(潜在的な全人格からの)「現実化」であると説明することを可能にする。
結論:持続の揺るぎなき直接性
本報告書は、「ベルクソン時間」が、単なる主観的な時間の理論ではなく、一つの包括的な形而上学体系であることを明らかにしてきた。その探求は、意識の「第一の実在」3としての「純粋持続」3の発見から始まり、その実在を歪曲する「空間化」2という知性の病理の診断へと進んだ。この診断に基づき、ベルクソンは「自由」3の問題を偽のジレンマとして解体し、アインシュタインとの対決 1 において哲学の固有の領域(質的なもの)を擁護した。さらにこの持続は、「エラン・ヴィタール」4として宇宙論的スケールに拡張され、最終的にはドゥルーズによって「潜在性」7の形而上学として再解釈された。
21世紀の現代において、私たちはアインシュタイン=ベルクソン論争の「二重のレンズ」1そのものの内を生きている。グローバルなネットワーク、金融、物理学は、アインシュタイン的な(あるいはそれ以前のニュートン的な)均質で空間化された「測定の時間」によって冷徹に支配されている。その一方で、このシステムが無視し続ける「生きられた体験」の質的な領域(=持続)こそが、私たちの生の意味の源泉であることに変わりはない。
ベルクソンによる「空間化」の批判は、すべてが離散的な「データ」へと還元され、計量化される現代のデジタル時代において、彼が生きていた機械の時代よりも、はるかに切実な響きを持っている。質的で、連続的で、相互浸透する経験の流れを把握するという、困難な方法論的営為としての「直観」3へのベルクソンの呼びかけは、神秘主義への逃避では決してない。それは、自らを忘却させようとする世界の中で、人間の存在の「第一の実在」3を取り戻すための、今なお最もラディカルな哲学的ツールの一つであり続けている。
引用文献
- アインシュタインとベルクソンの時間観の違い|無流アクタ – note https://note.com/rodz/n/n75db12a8e480
- ベルクソン哲学における「空間化」概念の諸相、その … – researchmap https://researchmap.jp/shuichiro-higuma/presentations/26007518/attachment_file.pdf
- 要約 ベルクソン『時間と自由』|【哲学・思想】一人読書会 – note https://note.com/guitardrums/n/na2e4434fd019
- ベルクソンのエラン・ヴィタールが現代AGI開発に与える哲学的示唆 … https://research.smeai.org/bergson-elan-vital-agi-development-philosophy/
- ベルクソン哲学における 我論の 義 性の問題 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/bitstreams/728fe2ba-da82-4aba-ba2b-e510dba685e9/download
- アインシュタインとベルクソンの時間に関する意見の相違って、何だったっけ? : r/askphilosophy https://www.reddit.com/r/askphilosophy/comments/nw3ezg/what_was_the_einsteinbergson_disagreement_on_time/?tl=ja
- 本性の差異について2・実在世界は潜在性でできている … http://sets.cocolog-nifty.com/blog/2018/04/2-1044.html
- ベルクソン『時間と自由』 – logical cypher scape2 – はてなブログ https://sakstyle.hatenadiary.jp/entry/20060319/1142754372



